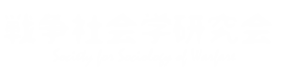第6回 戦争社会学研究会 大会プログラム
戦争社会学研究会 第6回研究プログラム
≫PDFファイルでもご覧になれます。第6回戦争社会学研究会大会プログラム
4月11日(土)
■個人報告
司会:青木秀男(社会理論・動態研究所)
・個人報告1(13:00~14:00)
冨永佐登美(長崎大学大学院)
「近代日本と「赤十字精神」の変容:看護婦生徒による答辞を手がかりとして」
・個人報告2(14:15~15:15)
高誠晩(京都大学大学院)
「南西諸島出身の行方不明者が台湾「二二八事件受難者」になるということ」
■特別講演(15:30~17:30)
「『従軍慰安婦問題』の論点 戦争社会学の視点から」
司会:福間良明(立命館大学)
講演:永井和(京都大学)
代表質問者:野上元(筑波大学)・木下直子氏(社会理論・動態研究所)
・趣意
いわゆる「従軍慰安婦問題」には多様な側面がある。様々な論者によって議論が激しく行われているが、むしろそこで見過ごされている論点や前提、盲点はないだろうか。このセッションでは、それを探すことに力を注ぎたい。それは、この「問題」に対し、この研究会、すなわち「戦争社会学」に何が出来るだろうかという問いにも繋がっている。
今回のセッションでは、京都大学の永井和氏を招き、まず基本的な論点を講演で示していただく。その後に、本研究会を代表して木下・野上の2名があらかじめ会員から募った質問を整理して永井氏に寄せる。当日は、会員の多様さに応じた論点が提起されるはずだろう。
■総会(17:35~)
■懇親会(18:00~)
4月12日(日)
■個人報告
司会:西村明(東京大学)
・個人報告3(10:00~11:00)
清水亮(東京大学大学院)
「海軍航空隊をめぐる地域の記憶のトポグラフィー――茨城県阿見町を中心に」
・個人報告4(11:15~12:15)
土門稔(関西学院大学大学院)
「江田島海上自衛隊教育参考館 近江一郎収集特攻関連資料からみる昭和21年~26年にかけての特攻兵士慰霊と遺族の実態」
==昼食休憩==
・個人報告5(13:15~14:15)
赤江達也(国立高雄第一科技大学)
「台湾の官立追悼施設・忠烈祠の形成と変容」
■テーマセッション(14:30~17:00)
「戦争と展示 ~大和ミュージアムをめぐって~」
司会・山本昭宏(神戸市外国語大学)
問題提起・一ノ瀬俊也(埼玉大学)
・山本理佳(愛知淑徳大学)
討論者・浜日出夫(慶應義塾大学)
・趣意
近年、アジア太平洋戦争を体験した世代の減少が問題になるなかで、戦争記憶の「継承」の問題が関心を集めている。非体験世代が戦争に触れる回路は、直接体験者から教育やメディアにシフトしたといえるだろう。
そこで関心が集まっているのが、戦争ミュージアムである。戦争の遺物を集めて展示し、来館者に見せるという行為は、戦争記憶の「継承」にいかに関与しているのだろうか。
本テーマセッションでは、呉市海事歴史科学館・大和ミュージアムに焦点を当てる。戦後史のなかの戦艦大和の存在、呉市における大和ミュージアムの位置づけ、そして展示のあり方などについて多角的に考察するセッションとなるだろう。
*会場
東海大学高輪キャンパス 4号館4206教室
交通アクセス:http://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/takanawa/
*大会参加費など
会員(専任・院生とも):2000円(+年会費)
非会員(専任・院生とも):3000円
年会費 有職者:2000円、その他のかた:500円
以上、頂戴します。整理しますと、
会員有職者・4000円
会員(院生など)・2500円
非会員・3000円
となります。
*懇親会
東海大学高輪キャンパス内の学生食堂で懇親会を開催いたします。
院生等の方々には、過度の負担がかからない程度の金額設定で考えております。
*聴覚障害等のある方で、情報保障の必要な方は、2月末日までに、下記の連絡先までお問い合わせください。(予算・人員の関係上、手話通訳等ではなくノートテイク等での対応とさせていただく可能性があります。また、できるだけ報告レジュメの電子ファイルでの事前提供に努めますが、報告者によっては事前提供や電子ファイルでの提供が難しい場合もあります。あらかじめご了承ください。)
*発表に際し、パワーポイントをご使用の場合は、ご自身のノートPCをご持参ください。
*場合によって多少の変更の可能性があります。
*問い合わせ先 戦争社会学研究会事務局宛( ssw.adm@gmail.com )
****************